オンラインにて「発達障害の方を施設にお迎えするための対応のヒント」というテーマで、研修を実施いたしました。
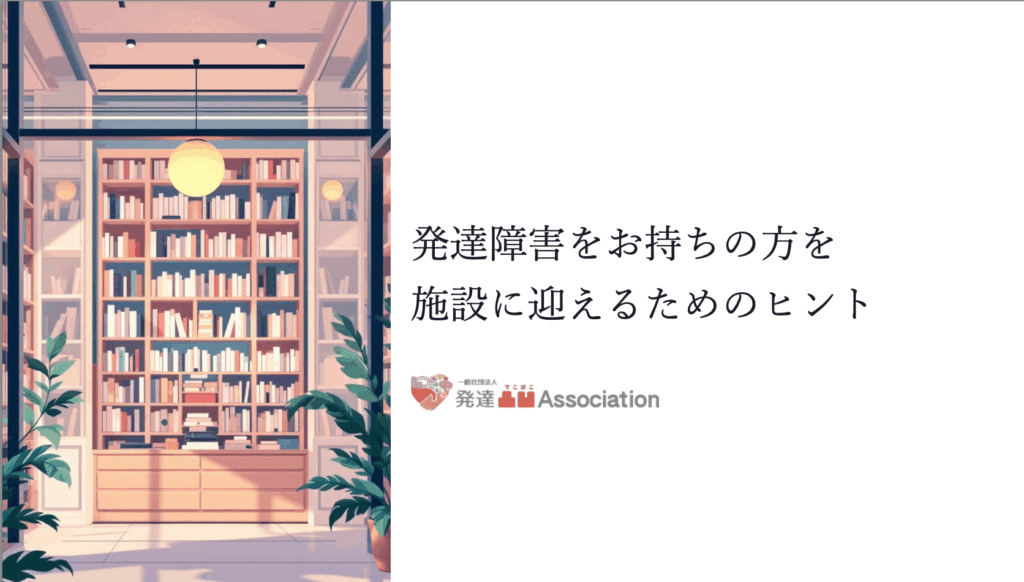
今回、ご依頼をいただいたのは全国の図書館運営の受託もされている丸善雄松堂様です。
実施内容
- 発達障害とは
- 特性と感覚の理解
- 年代別の特徴と、対応の基本
- 来客者対応
- スタッフとして自分の心を守る方法
今回の研修のポイントは、「幅広い年齢の発達障害、もしくは発達障害傾向のある方への対応のヒント」です。
普段は対象となる方の年齢がある程度限られているので、その年齢の方の特徴や対応方法についてお話しますが、今回は未就学児〜大人まで、と幅広い年齢層への知識が求められました。
事前に、現場の皆様にとっていただいた「アンケート」があったので、かなり具体的なお話ができました。
よくある悩みと解決策
アンケートの中で多かったのが、
- 説明、お願いが伝わらない
- 1種類の本や、人への執着
- 感情の高ぶり、激昂
そういった時に、どのような対応がベストなのか?というご質問が多くありました。
全体的に「仕事としてしっかりと対応したい」という気持ちが前提にあり、まずはその点に非常に感動いたしました。
「もっとよい対応をしたい」「もっと適切な対応ができる自分になりたい」という、お仕事に対する真摯な姿がアンケート全体に溢れていたのが印象的でした。
そのため、今回は「具体的な対応策」を中心にお伝えすることができました。
対応のフレームワークとして、
- 簡潔に伝える
- 視覚的に伝える
- 環境の調整
- 声がけの工夫
など、具体的な事例を解説しました。
今回の研修の特徴
今回の研修の特徴は、「接客」という点です。
これまでの発達障害に関する研修では、「長期的に関われる」ことが前提のため、長期的な目線での対応方法を解説することができました。
発達障害やグレーゾーンの方への対応方法は、「これが正解」というものを見つけるのが難しく、原因となっているものを推測していくつかの対応策を実施、検証していく・・というものが基本になります。
ところが今回の皆様は、「たった一度しか会わない方への対応」がほとんどです。
そのため、これまでの研修で伝えてきた対応方法とは、多少異なる点がありました。
「その時、その瞬間の対応」ができるようになることが、スタッフの皆様にとって有益です。
それでも、長期的な対応と変わらない部分もたくさんあるので、私もあらゆる視点からいろいろと考えてみました。
来館者も受け入れる側も、スムーズに安心してその「瞬間」を気持ちよく共有できるようになれば嬉しいです。
自分の心を守る方法
事前アンケートを拝見し、一番今回の研修で伝えなければならないと感じたのは、「対応する側の心を守る重要性」です。
皆様のコメントは、非常にお仕事に熱心で、「発達障害の方々に寄り添いたい」「理解したい」「よりよい対応をしたい」という気持ちに溢れていました。
でも、前述した通り一時的な「接客」の範囲では、今回お伝えした内容が確実に解決になるかはわかりません。
どんなに学び、理解し、寄り添い対応したとしても、思い通りにいかなかったり、逆に理不尽な思いをすることあると思いました。
「もっといい対応ができたのでは?」
と、後悔し自分を責めてしまうこともあるかもしれません。
また、「せっかくここまでやったのに!」とストレスがたまることもあるでしょう。
接客する側も人間です。
最後に、皆さんの心をしっかり守ることの大切さと、その方法もお伝えしました。
これは、私自身の「発達障害の子どもを持つ一人の親としての経験」と、「様々な人と関わりマネジメントしてきた経験」から実感することです。
当事者の方々も様々な困難を持ちながら生きていることは事実ですが、そこに関わる周囲の人々も非常に心をすり減らしていることが多くあります。
発達障害の方は敏感な方が多いので、そういった「空気」をよんでしまい、どうしていいかわからず状況が悪化することも少なくありません。
介護にも「レスパイトケア」という言葉があります。
これまでたくさんの親御さんや支援者さんを見てきて、関わる人達が良い状態でいることが、結果的に当事者の方にもよい影響を与える、ということを感じています。
特にこういった研修を受けた後は特に、「あの時、もっとよい対応ができたのでは」と思いがちです。
「その時、その瞬間にできたことが、その時の最善策」
どうか、自分を責めないでください。
今回のセミナーは、オンデマンドで500名近い方が受講してくださるとのこと。
このメッセージは最後にお伝えしましたが、是非この部分まで視聴していただけると嬉しいです。
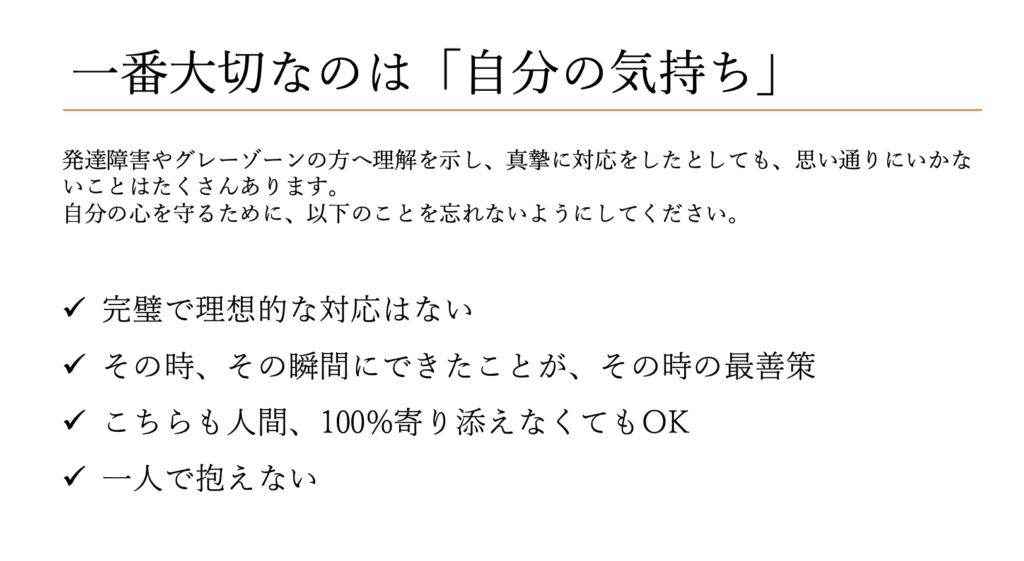
また新しい経験と学びをくださった、丸善雄松堂様には心より感謝申し上げます。

